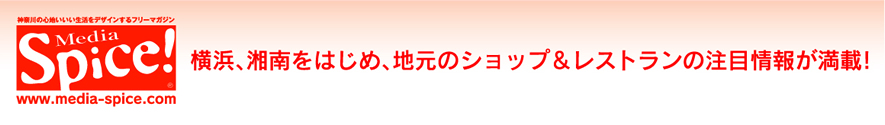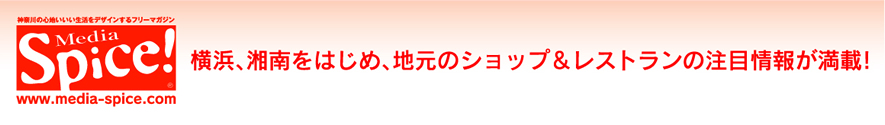|
 優雅なメロディがヴァイオリンの響きの美しさを際立たせる「あなたの中の私」は自身が書き、躍動感溢れるスパニッシュ・テイストの「過ぎ去りし日々」はピアノ奏者、北島直樹の作品で、ブルージーな50年代ジャズを思わせる「テンガロン・シューズ」はギター奏者、細野義彦が提供。寺井尚子さんの新作『アンセム』は収録曲のほとんどがバンドのオリジナルだ。 優雅なメロディがヴァイオリンの響きの美しさを際立たせる「あなたの中の私」は自身が書き、躍動感溢れるスパニッシュ・テイストの「過ぎ去りし日々」はピアノ奏者、北島直樹の作品で、ブルージーな50年代ジャズを思わせる「テンガロン・シューズ」はギター奏者、細野義彦が提供。寺井尚子さんの新作『アンセム』は収録曲のほとんどがバンドのオリジナルだ。
「去年の6月にこのバンドをつくったのですが、考えたのは、レギュラー・バンドでなくては出せない深みのあるサウンドを大切にしようということ。それでメンバーに 曲を書いてみない
という感じでリクエストして、次々にオリジナルができていったんです」
メンバーから渡される譜面に書いてあるのはコードとメロディだけだ。
「リズムも速さも書いてないんですが、そのほうが好きだったりするんですよね。スリルがあるじゃないですか。
“ここはドラムをブラシにしてさ”とか、どのように演奏するかを考えるのがすごい好きなんです」
寺井さんは4歳のときにヴァイオリンをはじめた。クラシックのソリストを目指し、レッスンに励む日々を何年も過ごしたが、中学2年のときに転機が訪れる。
「左手が腱鞘炎になってしまい、年に1度のコンクールが終わるとレッスンを休むようになりました。そうしたらいろんなジャンルの音楽を聴いてみようかなという気持ちになったんですよ。16歳のとき、ほとんどジャケット買いでビル・エヴァンスの『ワルツ・フォー・デビー』を買いました。こんな世界があったんだ。私はこれを弾きたい。私はヴァイオリンが弾ける。よし、やろう。それだけでしたね(笑)」
ジャズのヴァイオリン奏者として注目されつつあった94年、寺井さんは出演していたジャズクラブで、たまたま来店したピアニスト、ケニー・バロンと共演する。
「1年後、彼から自分のレコーディングに参加してくれないかと、オファーがあったんです。夢のような話でした」
エディ・ヘンダーソンをはじめとする一流奏者が顔を揃えたニューヨークでのレコーディングは、ケニー・バロンの作曲が遅れ、リハーサルができなかったこともあり、寺井さんにとって緊張の極みだった。
「ほかのメンバーは曲をすぐに覚えちゃうんですよね。だいたい2テイクで終わりました。予定されていた3曲を集中して演奏し、やっと終わったと思ったら、ケニー・バロンが私のブースに来て、“ナオコ、イメージだけでやってみないか”と言ったんです。“テンポもキーも決めないの”と尋ねると、“僕が弾くから思うままに弾きなさい。僕もそれに応えるから”と。目を閉じて、開いたときには演奏が終わっていたという感じの8分間でした。二人でエンジニアの部屋に行くと、いままでいっしょに演奏していたミュージシャンもいて、拍手喝采だったんですよ。何年間も自分のイメージしたものに向かって真っ暗なトンネルをずうっと走ってきたような感じでしたが、そのスタジオを出た瞬間にさっと光が射して、自分の信じた道は間違っていなかったという確信を得ました」
贈り物にしたい1曲として選んだのは、ミシェル・ペトルチアーニ、スティーヴ・ガッド、アンソニー・ジャクソンの『ライヴ・アット・ブルーノート東京』に収められている「home」だ。
「一音、一音から魂の入った音のエネルギーが感じられ、体の中を爽快感が駆けめぐります」
text by Akira Asaba
photo by Atsuko Takagi
|